これからの庵治石の需要について

庵治石や産地の現状について教えてください
現在、庵治石の供給は適宜適切に、順調に行われています。
ありがたい事に、「石」は有史以前から人類が必要として、使われてきました。その中でも庵治石はその美しさや石の持つ細やかさから繊細な加工ができる石として世界的にも高く評価されています。
庵治石開発組合は、山から採ってきた原石の庵治石を大量に扱っています。
石自体が持っている自然の力を活かし、石積みや海洋の埋め立てなど、穏やかな社会インフラ構築に使っていただきたいと思っています。また、魅力ある庵治石は時代の要請の中、新たな用途も開発されています。

若手には、産地の外で学んできてほしい
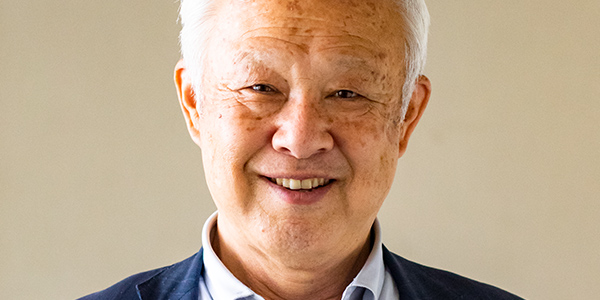
半世紀以上、この産地を見てきて、他に変わってきたところはありますか?
山から石を切り出すとき、昔は金梃(かなてこ)と人力でやっていた作業が、動力(索道ウインチ)になり、さらに機械(ブルドウザー、フォークリフト、ユンボ)に代わってきました。
昔と比べて格段に変わったことは「筋肉」をつかわなくなったことです。たとえば、トラックなんかも昔はハンドル切るのもチカラ(筋肉)が要りましたが、今はスルスルッといけますからね!山のしごとは“おとこのしごと”と云われていましたが今は女性もできるしごとになりました。
逆に昔と変わっていないところはありますか?
“洞察力”です。
自然の山(丁場)から石を切り出す丁場は日々変化しています。そのような状況の中、石を傷つけないように大事に切り出すためにも、この岩盤の中はどうなっているんだろうか!表面的な部分だけでなく。その奥を見抜く力が必要です。庵治の職人さんの“洞察力”は素晴らしいです。

代表理事として力を入れていきたいことは何でしょう?
それはもう「若手への移行」ですね。世代交代が自分の課題だと思っています。次世代への橋渡しというか・・・「そのために就任した!」というくらいの気持ちでいます。
若い人達に「外に出て、色々と見て学んでほしい」と思っています。そういう機会を作ったり、背中を押してあげられるようなバックアップを、組合として今まで以上にやりたいなと思っています。
後継者育成・技術の継承はなかなか難しい問題ですね
人間は石をずっと使ってきたわけで、日本人も先祖を祀るために石を用い、手を合わせられるものとして、石を用いてきました。そこには人類が“求める何か”がやっぱりあるんだと思うんですね。そういう“何か”があるからこそ「石に手を合わす」のだと思います。
ストーンフェアでやっている大丁場見学ツアーは大変人気があります。それは丁場に“求める何か”を観に来られておられるんだと思います。
石を採掘する我々の職業はそれに応えるしごとだと、矜持を持っています。
ここ庵治には人柄がよく立派な人が沢山います。だから心配していないんですよ(笑)。

大学卒業後すぐに家業である石屋の世界に入られたとのことですが、他に関心があった職業や業界はなかったのですか?
そうですね。他にやりたいことは余りなくて・・・「やりたい」というか「やらないかん」という思いが強かったですね。
趣味やプライベートの過ごし方などは?
あんまりプライベートがないので・・・趣味ナシ(笑)。「仕事が趣味」というと格好をつけとるみたいやけど、ゴルフもせんし・・・疲れたら指圧へいくくらいで、本当に趣味らしい趣味はないんです。

1956年生まれ。
大学卒業後、株式会社三好石材(1900年創業)に入社。現在は代表取締役会長
Xアカウント:@ajiishi148

